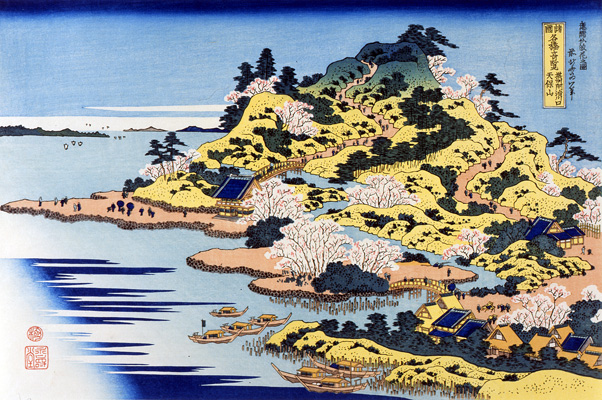富士見と富士見坂(4)の6 日暮里花見寺と文化11年のダイヤモンド富士(6)
修性院の庭造「岡扇計」または「岡扇斗」及び発起者「高田義石」の探索、さらに「日暮里(ひぐらしのさと)」の地名の起源についての一章である。
「扇計」を号した人物は複数存在する。例えば1675(延宝3)年徳川綱吉の代に祐筆をつとめた斎田元信で、1710(宝永7)年致仕(退職)後に扇計を号としているが、1720年9月19日(享保5年8月17日)に死去している。(註206)
他に俳号を「扇計」と号した人物があり、初期俳書に頻回に登場する。その在地は、1679年の大和宇陀の「谷氏」(註207)が最も早く、伏見(註208)、南都(奈良)(註209)、大坂(註210)、越後高田(註211)と続いていく。(註212)これらがすべて同一人物であるとは断言できないが、少なくとも扇計を俳号とする人物が関西圏内を移動しているように思われ、あるいは越後高田にも赴いたのかもしれない。高田義石の肩書である高田と合致しており注目されるが、上記の人物を同一人物と見ると、修性院作庭時には100歳近い年齢となり、不合理である。なお、宇陀松山藩の家老職をつとめた生駒氏は、もと谷氏であったということは注目される。(註213)
他に「扇斗」の名が、越後の南会木陸夜編の『藁人形』「云々子先生餞別」の中に見える。(註214)ただし「計」と「斗」はくずし字の字形が酷似しているため、誤記、誤読に基づくものである可能性がある。
初代都々逸坊扇歌は、姓は岡、歌の異体字「哥」もまた「計」「斗」と字形が似ており、「岡扇哥」は有力な候補のようだが、1804年生れということで、候補から外れる。
岡山城下の古町名に扇計町があり(註215)、羽柴秀吉による高松城攻めの折に旅籠屋をしていた藍屋扇計の名に起源をもつという伝説がある。(註216)雅号を称する際に、「漢名」といって姓を1文字の単姓とすることがあり、「岡扇計」には、岡山の扇計という趣意があるのかもしれない。
「高田義石」についても確実なことは分からない。現・八街市根古屋にある妙長山法宣寺本堂に俳句の献額があり、そのひとつ、安政二乙卯【1855】年卯月「真実庵評四季混題吟」の内に下総高田、高田、高田連として38句34人の俳句が献納されている。34人の俳号の内に、
「鶯や二声目には寒うなる 下総高田 之才
若竹や朝な朝なに雫おく 同 周月
広畑に人声多しそばの花 同 義石」とある。(註217)
高田義石の号は一致するが、年代が離れすぎている感がある。
献額に名の見える評者の真実庵は、額に「東部判者 抱義」とあり(註218)、江戸時代後期の豪商、俳人で守村抱儀の号。江戸浅草蔵前の札差で守村次郎兵衛といい、俳諧を京都の成田蒼虬、絵を酒井抱一、詩文を中村仏庵に学ぶ。名は約、字は希曾、通称は次郎兵衛、別号に鷗嶼、経解、松篁、交翠、山房、法号は真実庵隆然抱儀法子、小青軒の別号もあったといい、天保二十四詩家のひとりにかぞえられる。後出する『江戸名所花暦 初刷』は、彼の仮名序を付されており、『新訂江戸名所花暦』の校訂者である市古夏生は、彼が「資金を出して出版した」と推定している。(註219)妹も俳人の鶯卿(字は春葩、別号鶯渓、莫愁庵)。
守村抱儀は、晩年没落して越後に逃れるが、同所滞在中に記した『加茂日記』によれば、滞在先に「近在の俳諧同好者がひっきりなしに訪れ」たほか、江戸をはじめ各地から抱儀あてに添削を乞う書状が届き、その都度筆を入れて返書していることがわかる」という。(註220)蔵書家としても知られ、足代弘訓は「第一書物の多きは聖堂也、次浅草蔵前守村次郎兵衛也、和漢の蔵書十万巻あり、号を十万巻楼といふ、次阿州侯【阿波徳島藩蜂須賀家】也和漢の御蔵書六七万巻ありといふ、次塙蔵書皇朝の蔵書二万巻計あり、」と記している。(註221)明治政府は、旧幕府の富士見亭文庫を引継いだ紅葉山文庫の書籍をベースに浅草蔵前に浅草文庫を開設する。現在の国立公文書館の前身だが、何かしら守村抱儀との因縁が感じられる。
他にも義石の号は、松浦胡叟『かふと集』に「大浜 義石」という名が見え、俳人の分布から考えると、大浜は三河大浜と思われる。(註222)「大浜漁港は、南北朝時代(1336年~)から海運の要所としてその名が出てきています。米、酒、みりんなどの物資の集散地として、海上交通の重要な港として発達しました。当時は、水上輸送を仲介し、年貢の輸送・保管・販売や旅館を兼ねる問屋であった問丸があり、当地随一の港でした。(当時の問丸の存在がはっきりしているのは、伊勢の桑名、大湊、駿河の沼津ぐらいです。)」(註223)また、「矢作川河口での鋳物砂、水運の要地」でもあった。(註224)こうした地盤の上に「新川・高浜の三州瓦や乙川・成岩の知多木綿の生産を拡大し、矢作川右岸の棚尾には鋳物工場を、成岩の神戸川沿いには晒工場を展開させ、在来工業の中核地を形成してい」ったという。(註225)
次に、各地における作庭の状況についてふれると、京都の作庭家は、「庭造(作)」(にわつくり)と呼ばれた。中世において、相国寺や興福寺大乗院などの多くの石庭を手掛けた善阿弥の孫で、相国寺の庭を三代がかりで完成させた山水河原者の又四郎が、遣明正使にもなった相国寺鹿苑院住職の景徐周麟に「某、一心に屠家に生まれしを悲しみとす。故に物の命は誓うてこれを断たず、又財宝は心してこれを貪ぼらず」と語ったという。(註226)この言葉に如実に示されている通り、当時の作庭家は被差別民であった。元来「清目(きよめ)」を職掌としていた職能民が作庭を行うようになり、世界に誇りうる日本庭園の芸術世界を現出したのである。
藤田彰典氏によれば、京都では、樹木の生産農家、農家から商品を購入販売する植木屋と、彼ら作庭家の職掌は明確に区分されていたが、やがて植木屋が作庭に関与するようになり、田沼政権期に株仲間を編成して業を独占、農家の生産直売にも対抗している。(註227)藤田彰典氏の研究に先行して、山田光二氏は、植木屋の成立過程を「植木屋と庭手入れという関係がさかんになったのは明らかに江戸時代になってである」、「江戸時代の植木屋は二種類に分かれていた。
一つはもっぱら植木の栽培と販売を行う専門の植木屋である」、「さらにもう一つの植木屋は植木の栽培と販売の他に、庭造り、庭木の植込み、手入れなどを行なったものである。それゆえに植木職ともいわれていたのであろう。しかし、江戸中期を過ぎると、しだいに、庭造り、植木造り、庭木手入れ、植木売りなど、その業務を分化するようになった」と分析する。また「江戸の植木屋がしだいにその業務を分化していったのにたいし、京都では、植木栽培の販売と庭木手入れを行う植木屋と、それに庭造りを兼ねた植木屋の二種類しかないのである。さらにこれらの植木屋が仲ヶ間を結成し、仲ヶ間定法をつくって、それぞれの植木屋が得意先を持ち、互にその領分を侵さないようにしていた」という史実を明らかにした。(註228)また、一方の作庭家は「庭師」とも呼ばれるようになったという。(註229)
「扇計」の在地のひとつとして登場した大和宇陀松山は、旧幕領で商業地として栄えた地で、森野吉野葛本舗第11代森野家当主の(註230)初代藤助賽郭は、薬草に対する造詣が深く、高松藩の本草家の平賀源内とも親交があり、幕府採薬使の植村左平次とともに近畿一円から北陸地方まで数回にわたる採薬、調査旅行を行ない、『松山本草』(1768年頃成立)をまとめている。
徳川吉宗の漢方薬の自給自足と農事振興の施策に合致しているとし、褒賞として下賜された薬草や種を森野賽郭が自家の薬園で栽培し、享保年間【1716‐1736】に自宅の裏山に開いた森野旧薬園は、日本最古の薬草園のひとつで日本初の民間薬草園として知られている。薬園は、「宅地から小門をくぐって登っていくが背後は城山に連続し東西南の三面はよく日光をうけて地味きわめて良く、しかも排水もよく植物の栽培に好適で、250種類の薬草が現存している」(註231)
それらの薬草は小高い丘の急斜面から上にかけて栽培されており、「丘の上には茶室があり、宇陀野を一望することができ」るというから、日暮里花見寺の地形や造園方法とよく似ている。近くにある宇陀市大宇陀歴史文化館「薬の館」は、江戸末期に建てられた薬問屋旧細川家の住宅をそのまま利用したものであるが、細川家二代目の二女の長男友吉はこの館で生まれ、のちに藤沢家の養子となり、藤沢薬品工業株式会社を創立したという。(註232)森野賽郭の辞世の一首は
「賽郭はまだ死にもせず生きもせず春秋ここに楽しみぞする」
であったという。(註233)
大坂での造園の状況は、『懐中難波雀』(1679)によると、近世の大坂でも「庭作」を職業とする者もいたが、植木屋の名称で呼ばれることが多かったらしい。飛田範夫氏は、「大坂で植木を販売する者と作庭する者を合せて「植木屋」とよぶようになっていったのは、植木を販売するだけでなく依頼されれば作庭することが多かったからだろう」という。大坂では、武家、寺社、町人による庭園設営がさかんに行なわれ、1833(天保4)年には、淀川流末の浚渫事業を兼ねて天保山が完成。その築造にあたっては、庭園技術が応用されたという。飛田範夫氏によれば、
「『反故籠』(『大阪編年史一七』)によると、天保四年三月に天保山が完成すると大変なにぎわいになり、
川べりには日々二百艘・三百艘の屋形茶船、見物群集、陸路よりも数万人毎日〱の賑ひ、京都・近国より来人夥敷事に候
という状況になった」という。(註234)
標高4.53m、日本一低い山「天保山」の誕生である。天保山には天保山山岳会があり、「登頂」すれば「登山証明書」が発行されていた。(註235)ただし、2014年4月9日に国土地理院が発表したところによると、復興地図の作成にあたり、仙台市宮城野区にある日和山周辺の標高を調査したところ3mと確認され、日本一低い山に認定されたとの報道もある。(註236)いいことなのか、悪いことなのか線引きはできないが、大阪のいちびり精神、東北の粘り強さと、それぞれに「山」にたいする地元の愛着を感じる。
「扇計」の別の在地である越後高田は、高田平野の中心にあり、高田城の城下町、越後縮緬の生産地、集散地として栄え、総延長16kmに及ぶ雁木が残されていることで有名な町であり、玄翁(源翁)心昭によって砕かれた九尾狐由来の殺生石の破片の飛来地のひとつでもあり、この伝説がかなづちを「げんのう」と呼ぶ起源説話となっている。1666年2月1日(寛文5年12月27日)、高田は大地震に見舞われ、「城破損、潰家多し、出火あり、死者1,500人」という状況であったが(註237)、その復興工事により、城下町の町家に雁木と呼ばれるアーケードが完備されたという。(註238)
テレビドラマの水戸黄門は「越後のちりめん問屋の隠居光右衛門」を名乗っていたが、高田から旅をする人々は多く、蕉風の俳人、南嶺庵梅至は高田を出発して、松尾芭蕉の足跡をたどって奥羽地方を廻り、江戸から帰郷する旅に出かけ、その紀行文を『奥羽の日記』(1757(宝暦7)年)として句文集にまとめている。他に『伊勢みやけ』(1756頃)、『伊勢便』(1774)などの紀行文もあり、各地を旅したことがわかる。(註239)『諸国翁墳記』(1671)に「花見塚 越後高田春日町正輪寺ニ在 梅至建」とあり、南嶺庵梅至は高田に戻ったあと、正輪寺に松尾芭蕉をしのぶ花見塚を築造している。(註240)また、江戸と高田の間には「高田飛脚」と呼ばれる定期便の通信幹線があり、小林一茶も文通の手段として利用していた。
高田藩は、戊辰戦争時、薩摩、長州などの新政府軍が来越すると幕府の古屋佐久左衛門軍を攻撃して破り、「恭順」の姿勢を示した。高田藩は長岡、会津「討伐」の先鋒を命じられ、東北各地に参戦するが、常に徳川家康軍の先鋒をつとめた榊原康政の後裔が、討幕派の先鋒隊として徳川幕府の幕引きを行なう役を担ったことになる。これを拒否し、高田藩を脱藩した藩士たちは、神木隊を編成、後に彰義隊に合流、上野戦争、宮古湾海戦、さらに箱館(hak-casi*?)戦争を転戦した。戊辰戦争後、高田藩は会津藩士1,742名の捕虜収容を命じられるが、捕虜収容中に死亡した会津藩士の墓地は「会津墓地」と呼ばれ現存している。(註241)また、長岡を戦場とした北越戦争は、大仏次郎『天皇の世紀』で詳細に描かれているが、これが大仏次郎の絶筆となった。
法宣寺への献額に高田義石の登場する下総高田は、徳川家康領、内藤修理亮支配地、佐倉領、幕府領を経て、旗本戸田氏の知行地となる。1855(安政2)年の高田村家数は74軒という。(註242)高田村の俳家連が献額奉納した妙長山法宣寺は、現・八街市根古谷区にあり、同寺は不受不施派の日蓮宗寺院で、1457(長禄1)年、松戸平賀の本土寺7世日意上人によって創建され、上人が白牛に乗って説法している図と、市川の長谷山安国寺の曽谷教信の手になる日蓮像「生御影(しょうみえ)」が名高く、幕末から明治にかけては、門前に茶店が並ぶほど賑わったという。法宣寺は、須藤由蔵の『藤岡屋日記』によれば、1808(文化5)年、
「日礼上人作諫言生御影 日蓮大菩薩 下総埴谷妙長山法宣寺
五月十日ゟ六十日之間、浅草八軒寺町、中将山大仙寺ニて開帳」と、江戸浅草で開帳していることが分かる。(註243)比留間尚氏の調査によれば、法宣寺の江戸における出開帳は、元文2年7月16日‐9月16日 浅草幸竜寺にて下総根古谷村法宣寺 日蓮像曼荼羅(『開帳差免帳』)、宝暦11年3月13日より60日間 下総印旛郡塩谷村法宣寺 祖師像(『開帳差免帳』に年限未満であるがとくに差許す旨記載あり、『武江年表』に4月8日より浅草玉泉寺、法泉寺文書では開帳場所は浅草善立寺)、文化5年7月21日より60日間 浅草長遠寺にて下総印旛郡根古谷村 日蓮像(『開帳差免帳』)、文政10年3月11日より60日間 浅草玉泉寺にて下総根古谷村法宣寺 日蓮像(『開帳差免帳』に年限未満であるがとくに差許す旨記載あり)、天保13年3月11日より60日間 浅草宝蔵寺にて日蓮像(『開帳差免帳』に年限未満であるがとくに差許す旨記載あり)と記録されているという。(註244)このように頻繁な開帳が行なわれるのは、日蓮宗の法縁拡大を目的としたものと考えられている。
作庭に関与したふたりの身元は判明しなかったが、彼らの社会階級はどのようなものだったのか。江戸中期を過ぎて、町人を中心にした文化世界が誕生しつつあり、地方の在村文化に注目すると、かなり早い時期から識字階層の広範化が進む。また、俳諧というシンプルな形式をもった文学表現で間口の広い文化営為の登場は、富商、富豪、村役人など中上流の階層を新たな担い手として、広い層に浸透し、それが広範なネットワークを形成するようになり(註245)、その傾向はさらに進んでいった。そうした中で作庭に関与し、石碑を建立した二人は、武士階級ではなく、町人または農民その他の社会階級であった可能性がある。
さて、先に取り上げた「日暮里」の雅名の起源についてであるが、名前の発祥は、謡曲『鳥追舟』である可能性が高い。『鳥追舟』は作者不詳の古作であり、林和利氏は、永享から文明(1429‐1487)頃の成立と推定しており、薩摩国の民間伝承である日暮長者伝説に取材した郷土色の濃い曲であるという。(註246)日暮長者伝説の文献的初出である『麑藩名勝考 薩摩国部第二』(1795)には、
「同郷【薩摩郡隈城郷】東手村
○ 日暮里(ヒグラシノサト)〔謡本鳥追船○按に、日暮てふ地名世に多し、茅蜩(ヒクラシ)の多き処に因しなるへし、〕」として、謡曲の梗概を記述する。(註247)
また、薩摩藩藩主島津斉興の命で編纂された『三国名勝図会 巻之十一』(1843)には、
「日暮の里〔地頭館より巳方、八町余、〕東手村称名寺の後にあり、縦二町、横一町許の岡阜なり、今は林叢、或は陸田となれり、むかし日暮の長者といふし人の居住せしといひ、此処を日暮殿とも、又は日暮の城など呼り、土俗の伝へに、日暮の長者、宮里村の内なる清水といへる所の女を娶り、男女二人を生し後に離婚して、継妻をを娶りしに、其継妻性凶悪不仁なる女にて、日暮長者在京せし時、前家児(ゼンハラノコ)二人に遇するや極めて残忍苛刻にして、鳥追舟を製し、毎日に是に乗せて、水田の鳥を追せければ、姉弟其苦辛に堪へず、遂に身を投て川に沈めり、里人深く是を哀惜し、此二人の屍を埋め、墓の表に𣜰樹(タブノキ)を植たるが、歳を経て大木となりて、鳥追の叢といひしとかや、」「又此二人の生母(ジツボ)の里、宮里村に、母逢川あり、其渡口を母逢の渡と号す、亦二人の子、母を慕ひて此川涯に至り、岸を隔て母に見(マミ)へ、甚た悲嘆せるよりの名なりとぞ、」とある。継子いじめ譚と母恋物語の複合した悲話である。
なお、後文には「偖も此日暮の里と申は、前には大河流れ、末は湖水につゞけり、此湖より群鳥あかつて、うらむかひの田をはみ候間、毎年鳥追舟をかさり、田づらの鳥を追せ候」と説明している(註248)が、薩摩郡はツルの飛来地で有名な出水平野の出水市に接続する。なお、柳沢信鴻の『宴遊日記』によれば、六義園中の泉水にツルが飛来しており、営巣、繁殖の観察記録が載っており、雛が巣立った時には祝いの食事を作り、上邸にもおくっていた。
また、薩摩は、日暮里と同様「諏方」と表記する諏訪明神社が多いので知られているが、こちらの日暮の里の近隣にも、諏方大明神社(東手村)、諏方大明神廟(東手村)、諏方大明神社(宮里村)が所在することは注目されるべきであろう。
家族の崩壊と母恋のモチーフは、謡曲『藍染川』にも展開される。『藍染川』は、渡辺匡一氏によれば、冷泉家流伊勢物語注(註249)が起源であると考えられている。(註250)鳥居明雄氏は、物語の中から「北野天神信仰圏での一族の再会・再結合」という構造を析出し、そこに「血縁共同の無化と擬制性」を見てとり(註251)、石井倫子氏は「紐帯たるべき父の不在ゆえにひとたびは崩壊の危機に瀕した「家」が、父その人によってその絆を取り戻すまでの“「家」再生の物語”として読み直すことができる」とする。(註252)
『鳥追舟』における家族の崩壊も日暮長者が土地訴訟のため京都に赴いたことが原因であり、いずれの家族もその崩壊の場は京都にあり、本来の在地日暮の里や「西下」の旅の目的地大宰府は、物語にとって架空性の強い付随的な要素であるに過ぎず、極論すれば、どの場所にあっても成立するということができる。そうであるならば、『鳥追舟』も薩摩地方の民間説話が起源なのではなく、謡曲のストーリーを展開する場所に地方色を与える脚色の方が先行し、謡曲に語られた地方へ物語の場が逆輸入され、伝説として定着したと見るほうが正しいかもしれない。
石神井川の旧流路、あるいは石神井用水の雅名である「音無川」は、熊野信仰によって命名されたことは異論のないところであるが、新堀村に与えられた「日暮里」の名は謡曲『鳥追舟』に由来し、谷田川の下流の雅号である「藍染川」の名も、この謡曲、あるいは後に浄瑠璃で語られた『藍染川』に由来するものであろう。
柳沢信鴻が郊外閑歩で、日暮里を盛んに訪れたのは、3ヶ寺の作庭の終った、まさにこの時期である。そしてこの時代は田沼時代といわれる時期にあたる。
田沼意次は、南鐐二朱銀という計数銀貨の創鋳により、金貨体系と銀貨体系の貨幣体系を統合し、地域間商品流通の再編成を目論んだ株仲間政策を推進する。(註253)さらに、銅座などの専売制の実施、鉱山開発、銅や俵物などの代替輸出商品による外国との貿易の拡大、下総印旛沼の干拓に着手する等、経済の外延的拡大を目指す積極的経済政策を展開、世界史的概念としての重商主義に相当する諸政策を実施した。ちなみに俵物とは、煎海鼠(いりこ)、乾鮑(ほしあわび)、鱶鰭(ふかひれ、幕末になって加わる)の海産物で、現在でも中華料理の高級材料である。1783年、ロシア帝国の脅威を訴え、仙台藩藩医の工藤平助が幕府への建白書ともいえる『赤蝦夷風説考』を板行、これに対応して田沼政権は蝦夷地の幕府直轄化と積極的開発を計画、蝦夷地調査のために最上徳内らによる幕府の探検隊を作った。
「鯨油ぶっかけ飯を共に食らい、衣服をまとい、寝食を共にした」(註254)、「最上徳内が北方を探検する際にアイヌの人達と寝食を共にし、アイヌの協力があって偉業を成功させることができました」(註255)という中での探検だったが、最上徳内自身は強烈な同化思想の持主であったという。勘定奉行松本秀持は、アイヌ民族に農業指導を行うとともに、労働力の不足分は、弾左衛門から「当時取極支配仕候武蔵、上野、安房、上総、下総、伊豆、相模其外、下野、常陸、陸奥、甲斐、駿河の内罷在候長吏非人共ども、人別高三万三千人余、此内七千人程は場所え引移し、新開為レ仕可レ申候」という回答を得たのを基礎に、「諸国に罷在候長吏非人等、人別高凡弐十三万人程可レ有レ之哉、此内より新開場え為引移候人数、凡積六万三千人程、都合七万人程引連」と被差別民を蝦夷地に投入することを計画する。(註256)
いつの時代にも彼ら被差別民は、権力のいいように扱われようとする。狭山での女子高校生殺害事件の犯人として石川一雄青年がフレームアップ、逮捕され、冤罪により死刑を宣告されたのも、部落差別に基づく権力犯罪である。部落差別は、現在でも解決されていない深刻で残酷な人権侵害である。なお、最上徳内の墓は、駒込蓬莱町の蓮光寺にある。
しかし、田沼政権が直面したのは、1772年4月1日(明和9年2月29日)に発生した明和の大火による江戸の大被害である。このとき焼失した町数は904、死者数14700、行方不明者数4060を数えている。(註257)また、1783年、浅間山の大噴火という「自然大災害」に加え、18世紀半ばから19世紀初頭にかけて、「全地球的に寒冷気候が支配した小氷期(リトル・アイス・エイジ)」(註258)による夏季の気温低下によって天明飢饉が起こる。新中国の文化大革命直前のような状況である。
この年は、浅間山だけではなく、アイスランドのラーカギーガル(Lakagígar)火山、グリムスヴォトン(Grímsvötn)火山がスカフタ川の炎(Skaftáreldar)と呼ばれる大噴火を起こし、800万トンのフッ化水素ガスと1億2000万トンの二酸化硫黄ガスが噴出、ヨーロッパにおける直接的な健康被害、家畜被害、農産物被害は深刻で、また、大量のエアロゾルの放出による気温低下により、ヨーロッパでは、その後数年にわたって異常気象をもたらされた。(註259)
同年には、他にシチリア(シチリア語、イタリア語Sicilia)のストロンボリ(シチリア語Struògnuli、伊Stromboli)火山、アイスランド(Ísland イーストラント、現 Lýðveldið Ísland)のレイキャネース(Reykjanesskagi)火山、イタリアのヴェスビオ(Vesuvio)火山等が大規模な噴火を起こし、これらに起因する異常気象で、北半球を中心に多くの死者が発生、労働人口の減少も生じ、フランスでは、1785年から食糧不足が発生したが、しばらくぶりの豊作となった1787年、ブルボン朝フランス王国政府は、国庫破綻を回避するため、備蓄の小麦輸出を強行する。しかし翌年は大凶作となり、1789年7月14日のフランス大革命の引金を引く直接の契機になったといわれている。(註260)
同じ北半球域に属する日本もそれらの影響を受けており、古日記の天候記録から18・19 世紀の江戸の気温を復元したMikami Takehiko(三上岳彦)氏によれば、「Cool episodes in the 1780s, 1830s and 1900s are in accordance with poor rice harvests and severe famines.」(註261)といい、1780年代に低温のピークがあったことを論証、財城真寿美氏、三上岳彦氏は「この寒冷な気候は,江戸だけでなく米どころの東北でも同様の傾向であった。そして,当時の江戸は東北から運ばれる米に依存していたため,食糧不足が深刻化し,米以外の物価も上昇した。さらに,江戸での食糧不足や米価の高騰が地方にも波及し,地方での食糧難,そして江戸への難民流入により,飢饉が全国的に深刻化していったと考えられている。」とする。(註262)
当時の米作の限界地における不作は、国内総収量の絶対的減少をもたらし、純粋消費地の江戸に深刻な影響を及ぼし、前年の大火災からの復興途中にあった大都市は、その脆弱な基盤をさらけ出すことになった。食糧の端境期になる1787年5月には、江戸、大坂など当時の主要都市を中心に「天明の打ちこわし」と呼ばれる激烈な市民蜂起が起きている。また、1789年5月はじめ、アイヌ (*Aynu)民族によるクナシリ (*Kinashir)・メナシ (*Menas)の戦いが勃発する。こうした社会全体の動揺の中で、幕府内での権力闘争は、田沼意次の失脚と、松平定信による政権掌握によって決着を見る。
※2015年12月26日、石川一雄さんのお名前を誤記していたのを訂正しました。
註206 『寛政重修諸家譜』巻第四百、高柳光寿 岡山泰四 斎木一馬編集顧問 千鹿野茂編『新訂寛政重修諸家譜 第7巻』続群書類従完成会 1965
註207 三田浄久『河内鑑名所記』1679、谷氏との注記あり、今栄蔵編『貞門談林俳人大観』中央大学出版部 1989による
註208 『俳諧大三物』井筒屋庄兵衛重勝 1689、池西言水『俳諧前後園』井筒屋庄兵衛 1689序、池西言水『新撰都曲』井筒屋庄兵衛1690、『元禄五年歳旦集』井筒屋庄兵衛 1692、以上、雲英末雄監修 佐藤勝明 伊藤善隆 金子俊之編『元禄時代俳人大観 第1巻 貞享元年~元禄10年』八木書店 2011による
註209 三上和及『俳諧雀の森』皇都書林 1690、三上和及『俳諧ひこはえ』皇都書賈 新井弥兵衛 小佐治半左衛門 1691、以上、雲英末雄監修 佐藤勝明 伊藤善隆 金子俊之編『元禄時代俳人大観 第1巻 貞享元年~元禄10年』八木書店 2011による、流木堂行水『元禄百人一句』井筒屋庄兵衛 1691、大内初夫 桜井武次郎 雲英末雄『元禄俳諧集』新日本文学大系 第71巻 岩波書店 1994による
註210 若山烏順水『俳諧渡し舩』井筒屋庄兵衛 1691、雲英末雄監修 佐藤勝明 伊藤善隆 金子俊之編『元禄時代俳人大観 第1巻 貞享元年~元禄10年』八木書店 2011による
註211 南会木陸夜『藁人形』1704、『新潟県史 資料編11 近世六 文化編』新潟県 1983、上越市史編さん委員会『上越市史 資料編4 近世一』上越市 2001による
註212 以上の検索にあたっては、『新潟県史 資料編11 近世六 文化編』新潟県 1983、今栄蔵編『貞門談林俳人大観』中央大学出版部 1989、大内初夫 桜井武次郎 雲英末雄『元禄俳諧集』新日本文学大系 第71巻 岩波書店 1994、越佐古俳書研究会編『近世越佐の俳書 第一巻 寛延以前』高志書院 1998、上越市史編さん委員会『上越市史 資料編4 近世一』上越市 2001、雲英末雄監修 佐藤勝明 伊藤善隆 金子俊之編『元禄時代俳人大観 第1巻 貞享元年~元禄10年』八木書店 2011、雲英末雄監修 佐藤勝明 伊藤善隆 金子俊之編『元禄時代俳人大観 第2巻 元禄11年~宝永4年』八木書店 2011を参照した
註213 『奈良県宇陀郡史料』奈良県宇陀郡役所 1917
註214 『新潟県史 資料編11 近世六 文化編』新潟県 1983、上越市史編さん委員会『上越市史 資料編4 近世一』上越市 2001
註215 松平亮『東備郡村誌』天保期(1831~1845)、テクストは『森田敬太郎編纂『吉備群書集成 第弐輯 地誌部 中』吉備群書集成刊行会 1921による』
註216 高取久雄『岡山秘帖』吉田書店 1931、初出は「岡山市百余町の町巡礼」『岡山新聞』1930‐1931連載 の可能性がある
註217 八街町史編纂委員会『八街町史』千葉県印旛郡八街町 1974、「6. 俳句の献額」高田の歴史を尋ねる会『たかだ』創刊号 1999年3月、千葉市議会議員みす和夫後援会サイトによる
註218 八街町史編纂委員会『八街町史』千葉県印旛郡八街町 1974、抱儀は「抱義」字で記されることもある
註219 市古夏生「解説 二 底本と諸本」市古夏生 鈴木健一校訂『新訂江戸名所花暦』ちくま学芸文庫エ4 1 筑摩書房 2001
註220 関正平「加茂の風土記 江戸の俳諧師守村抱儀の来訪」『広報かも』No.618 2007年12月
註221 足代弘訓『伊勢の家つと』『日本芸林叢書 第5巻』六合館 1928
註222 雲英末雄監修 佐藤勝明 伊藤善隆 金子俊之編『元禄時代俳人大観 第2巻 元禄11年~宝永4年』八木書店 2011
註223 「大浜漁港について」愛知県公式サイト
註224 荒木国臣『三州地場産業発達史―鋳物機械工業・繊維・粘土瓦・醸造業―』赤磐出版 2006
註225 碧南市「碧南市環境基本計画(改定版)(平成 25 年 11 月 21日現在)」2013
註226 「鹿苑日録」1489年6月5日条、東京大学史料編纂所『大日本史料 第八編之三十二』東京大学史料編纂所 1983所収
註227 藤田彰典「京都の植木屋仲間」『社会科学』23号 同志社大学人文科学研究所 1977
註228 山田光二「植木屋仲ヶ間について」『日本史研究』第95号 日本史研究会 1968年1月
註229 飛田範夫『大坂の庭園 太閤の城と町人文化』学術選書058 京都大学学術出版会 2012
註230 高橋京子『森野藤助賽郭真写「松山本草」―森野旧薬園から学ぶ生物多様性の原点と実践―』大阪大学出版会 2014 によれば10代という
註231 森野旧薬園『文化財史跡 森野旧薬園の栞』パンフレット、「森野旧薬園」大和の神社サイトによる
註232 永縄厚雄「館長の黙して語らず 薬の歴史探訪~莵田野を訪ねて~(2009.12.04)」エーザイ株式会社くすりの博物館公式サイト
註233 大久保信治「森野賽郭と薬園の成立」木村博一先生退官記念会編集『地域史と歴史教育』木村博一先生退官記念会 1985
註234 飛田範夫『大坂の庭園 太閤の城と町人文化』学術選書058 京都大学学術出版会 2012
註235 天保山山岳会公式サイト
註236 テレ朝news、『讀賣新聞』による
註237 新潟県『新潟県耐震改修促進計画』2007
註238 谷沢明「【高田】雁木の続く町並みを残す仕掛け」愛知淑徳大学 谷沢明研究室サイト
註239 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国文学研究資料館 日本古典籍総合目録データベースによる
註240 『諸国翁墳記』橘屋治兵衛 義仲寺蔵版 1671、大学共同利用機関法人人間文化研究機構国文学研究資料館電子資料館による、「正輪寺(上越高田)」いきあたりばったり!サイト
註241 「高田藩年表」上越市公式サイト 2011、「会津藩士ら眠る 会津若松から訪問者」『上越タイムズ』2010年4月20日
註242 高田の歴史を尋ねる会『たかだ』創刊号 1999年3月、千葉市議会議員みす和夫後援会サイトによる
註243 『藤岡屋日記 第二』文化5年当年開帳条、鈴木棠三 小池章太郎編『近世庶民生活史料 藤岡屋日記 第一巻』三一書房 1987による
註244 比留間尚「江戸の開帳」「江戸開帳年表」西山松之助編『江戸町人の研究 第2巻』吉川弘文館 1973による、法宣寺文書は『八街町史料 第3集』千葉県八街町史編纂委員会 1966に収載されている
註245 八鍬友広「近世における文字文化の地域的浸透 十八世紀前半における越後の俳諧文化と関連して」『国立歴史民俗博物館研究報告』第97集 国立歴史民俗博物館 2002年3月
註246 林和利「謡曲「鳥追舟の成立をめぐって―日暮長者伝説との関連―」『鹿児島女子大学研究紀要』第6巻第1号 鹿児島女子大学 1985年2月、林和利「能・狂言の生成と展開に関する研究」早稲田大学審査学位論文(博士)1998、林和利『能・狂言の生成と展開に関する研究』」世界思想社 2003
註247 白尾国柱『麑藩名勝考』1795、テクストは鹿児島県維新史料編さん所編『鹿児島県史料 麑藩名勝考』鹿児島県 1972によるが、原文「茅蠕」は、国文学研究資料館所蔵和古書・マイクロ/デジタル目録データベース 大和文華館蔵本の影印を参照し、「茅蜩(ヒクラシ)」に訂正した
註248 五代秀尭 橋口兼柄編『三国名勝図会』1843、テクストは『三国名勝図会 四』山本盛秀編纂発行 1905による
註249 妹尾好信 辻野正人 森下要治校『定家流伊勢物語千金莫伝(広島大学蔵)』『翻刻 平安文学資料稿』第3期第1巻 広島平安文学研究会 1995
註250 辻野正人「中世伊勢物語注と『藍染川』―太宰府安楽寺・今川了俊・飛梅説話」『古代中世国文学』7号 広島平安文学研究会 1995
註251 鳥居明雄「能の終焉―「藍染川」と「水無瀬」の世界」日本思想史懇話会『季刊日本思想史』第24号 ぺりかん社 1984
註252 石井倫子「解体する「家」とその再生―〈藍染川〉の世界を中心に―」『日本文学』52号 日本文学協会 2003
註253 新保博 斉藤修「概説 一九世紀へ」『日本経済史 近代成長の胎動』岩波書店 1989
註254 大成建設週刊文春コラム「立ち話」「不屈の北方探検家・最上徳内(3)」『週刊文春』2007年10月25日号 文芸春秋 2007
註255 「最上徳内記念館」村山市公式サイト
註256 磯崎康彦「生誕250年 松平定信公伝43 外交と蘭学・アイヌ騒乱(2)」『福島民友』2009年3月4日
註257 「天明の大火」wikipediaによる
註258 速水融 鬼頭宏「庶民の歴史民勢学」『日本経済史 近代成長の胎動』岩波書店 1989
註259 Richard Stone「Iceland’s doomsday scenario?」『Science』Vol. 306 no. 5700 2004 Nov 19
註260 Vincent Courtillot 「New evidence for massive pollution and mortality in Europe in 1783–1784 may have bearing on global change and mass extinctions」『Geoscience』337号 2005、 Lee Siebert, Tom Simkin, Paul Kimberly『Volcanoes of the World Third Edition』University of California Press 2011、上前淳一郎『複合大噴火 1783年夏』文芸春秋 1989
註261 Mikami Takehiko「Long term variations of summer temperatures in tokyo since 1721」『Geographical reports of Tokyo Metropolitan University』31号 首都大学東京 1996年4月
註262 財城真寿美 三上岳彦「東京における江戸時代以降の気候変動 Climate Variations in Tokyo since the Edo Period」『地学雑誌』122巻6号 2013年12月